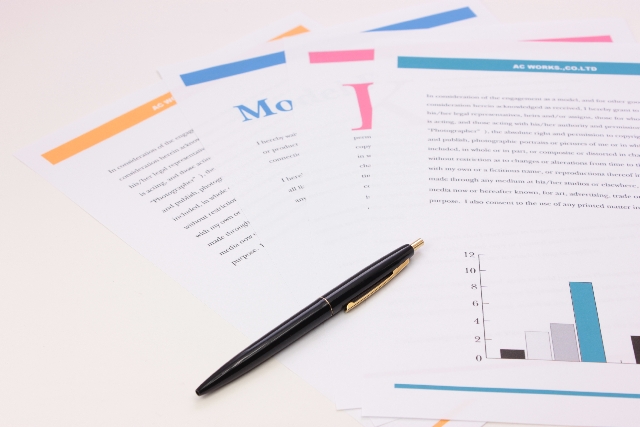


【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
失業保険をもらっていますが、
8月30日に、採用通知が届けられました。
でも、実際に働くのは、10月1日からです。
この場合、9月30日まで、失業保険をもらう事は可能でしょうか?
8月30日に、採用通知が届けられました。
でも、実際に働くのは、10月1日からです。
この場合、9月30日まで、失業保険をもらう事は可能でしょうか?
採用おめでとうございます!
大丈夫です。今現在失業手当を受給されている状態ならば(給付制限中とかではなく)入社日の前日までは失業手当は支給されます。
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし条件にマッチして再就職手当の申請ができるのであればハローワークから申請用紙を貰って下さい。
大丈夫です。今現在失業手当を受給されている状態ならば(給付制限中とかではなく)入社日の前日までは失業手当は支給されます。
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし条件にマッチして再就職手当の申請ができるのであればハローワークから申請用紙を貰って下さい。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
健康保険被扶養者調書について。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
期間限定派遣の失業保険給付について
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。
建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。
雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。
前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。
もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。
元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?
生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。
建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。
雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。
前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。
もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。
元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?
生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。
特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。
念のため、ハロワで確認して下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。
念のため、ハロワで確認して下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
関連する情報